童話館スタッフ思い出・イチオシ この1冊 第8回
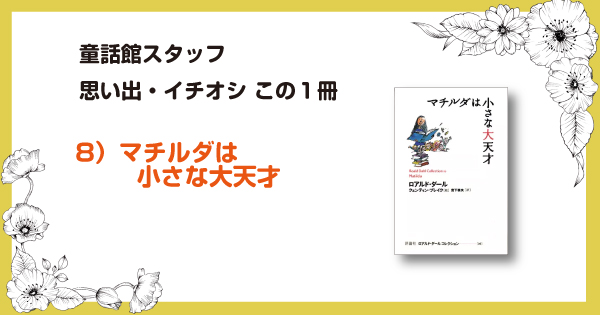
賢く、利口で、「大天才」の少女マチルダ。
けれど、両親はその才能に気づかないどころか、やっかい者扱い。その才能をつぶすような言動ばかりをする日々です。そして、マチルダが学校へあがると、そこにもまた横暴な校長先生が…。
理不尽すぎる大人たちに立ち向かうマチルダが愛らしく、とにかく応援したくなる、そして最後はスカッとする物語です。そして、著者のロアルド・ダールといえば、ブラックユーモアたっぷりの奇想天外なストーリーが魅力。この作品も、そんな魅力にあふれています。
この本に私が出会ったのは、小学校高学年のころ。近所のスーパーの一角にあった、小さな「子ども図書館」でした。そこには“図書館のおばちゃん”がいて、大好きな場所のひとつでした。
おばちゃんと、ひとことふたこと言葉を交わす時間も好きで、「その本好きなの?この本はもう読んだ?」と押しつけるわけでもなく、スッと軽やかにおすすめの本を伝えてくれる、そんなやりとりが心地いいものでした。
『マチルダは小さな大天才』もそんなやりとりのなかで出会った1冊。それまでの私は、学校の図書室で伝記を借りたり、父が買ってくれた古典童話を読んだりはしていたものの、海外のファンタジー作品にはあまりふれていませんでした。ですから、そんななか手にしたこの本はまさに衝撃的。「こんなおもしろい本があるんだ!」と夢中になって読んだ記憶が、今でも鮮明に残っています。
当時の私は、友だちとの関係も、両親との関係も、少しむずかしくなっていて、子どもなりにモヤモヤすることも抱えていました。そんな状況のなかで、賢く知的で、かわいいけれどちょっぴり皮肉っぽい小さなマチルダが、どうしようもないほどの理不尽に立ち向かっていく姿に、悲しくなったり、ワクワクドキドキしたり、物語のなかにのめりこんで、自分が抱えている理不尽やモヤモヤとも一緒に戦っているような気持ちだったのかもしれません。
それからは、ロアルド・ダールの大ファンになり、海外のファンタジー作品も大好きになり、むさぼるようにファンタジー作品を読みました。そのころの私にとって、本を読むことはきっと“現実逃避”の一環。物語の世界で、主人公と一緒に冒険したり、気持ちを共有したりすることが、自分の心を安定させる大切な手段になっていたように思います。もちろん、それが果たして健全なことだったのかはわかりませんが、それでも「何かあっても、本があればだいじょうぶ」、そんな存在に出会えたことは、救いです。そのきっかけとなってくれた『マチルダは小さな大天才』は、今でもだいじにしている1冊です。
中学生になり、子ども図書館に行くことも少なくなり、そうしているうちに閉館。通った期間はそんなに長くはありませんでしたが、あの場所は、私にとってファンタジーの世界そのものだったように思います。
そして今ふり返ってみると、おばちゃんは、なにげない会話のなかで、私の年令やようすを見ながら、そのときの私にぴったりの本をすすめてくれていたのかもしれません。すすめてくれた本に“はずれ”はなく、「このおばちゃん、いったい何者なんだろう…おもしろい本をたくさん知ってる…」といつも思っていました(笑)。
「童話館ぶっくくらぶ」のお子さんたちも、毎月の絵本や本との出会いをきっと楽しみにしてくれていることと思います。あのころの、私にとっての“図書館のおばちゃん”のように、「この本好き!」に出会うきっかけに、「童話館ぶっくくらぶ」がなれますように、と願っています。
(担当:G)
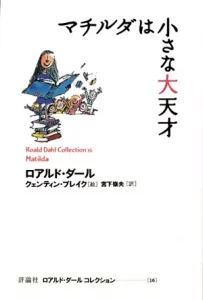 『マチルダは小さな大天才』
『マチルダは小さな大天才』
ロアルド・ダール/作
クェンティン・ブレイク/絵
宮下嶺夫/訳
評論社
「童話館ぶっくくらぶ」での配本コース ▶「小さいぺんぎんコース」(およそ11~12才)
この記事をシェアする
